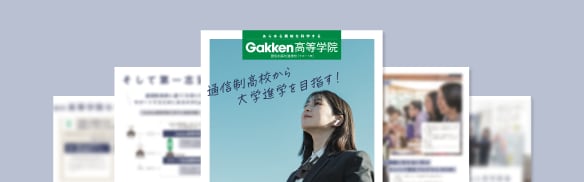高校の調査書とは?大学受験に必要な書類の中身と入手方法まで
2025.05.09

-
進学・進路でお悩みの方
-
授業料・詳細を知りたい方

高校の調査書は、大学等への出願において欠かせない書類です。
調査書の項目は、受験生自身はもちろん保護者にも知ってもらうことで、出願準備の手助けになります。
本記事では、調査書の項目など、基本的なことから受験における重要度、さらには実際の入手方法まで、調査書に関することを解説していきます。
2025年度の受験から変更になった点も含め、最新の情報を詳しくご説明しますので、受験を控えている方は、ぜひ参考にしてください。
高校の調査書とは
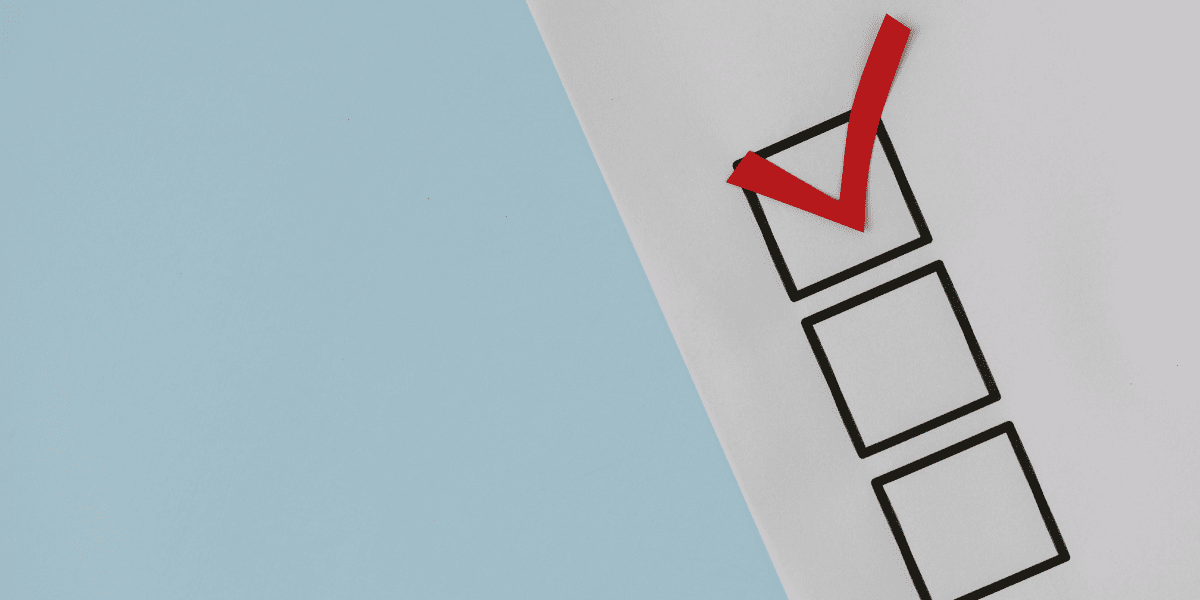
高校の調査書は、あなたの学習活動や高校生活について記載された文書です。調査書には、成績だけでなく、出席状況・部活動・学校行事への参加状況など様々な項目が記載されています。
大学受験においては、ほぼすべての入試形態で提出が求められる書類であり、推薦入試であれば合否を左右する可能性もあります。
調査書は「内申書」とも呼ばれ、高校3年間(または在学期間)の学習成果や行動の特徴など、総合的に記録されています。。
提出先の大学ごとに必要となるため、高校への申請を確実に行うことが大切です。
高校の調査書の記載内容の中身は全部で9項目

調査書には高校生活の様々な側面が記録されており、大学入試において重要な役割を果たします。そんな高校の調査書には何が書かれているのでしょうか?
記載内容は全部で9つの項目に分かれており、受験生自身の特徴や学校生活の取り組みを表しています。
- 氏名・住所・在籍校名・入学年度・卒業見込み年度
- 教科・科目ごとの学習記録
- 教科ごとの成績状況
- 成績の評定平均値
- 「総合的な探究の時間」における活動内容と評価
- 特別活動に関する記録
- 指導上参考となる事項
- 備考欄の記載内容
- 出欠状況の記録
氏名や卒業見込み年度などの基本情報
調査書の最初の部分には、基本情報が記載されています。
ここには氏名、住所、性別といった個人情報に加え、在籍している学校名、入学した年度、そして卒業見込みの年度が明記されています。
これらの情報は単なる事務的な内容に思えるかもしれませんが、受験生の基本的なプロフィールを証明するための重要な項目です。
教科・科目ごとの学習記録
この項目には、学習した教科・科目と評定が「数学Ⅰ:評定4(2単位)」「英語コミュニケーションⅠ:評定5(3単位)」などの形式で記載されます。
この記録は受験生がどのような学習を行い、各科目でどの程度の成果を上げたかを示す重要な指標となります。
また、履修した科目の種類や難易度も、受験生の学習に対する姿勢を表す要素です。
教科ごとの成績状況
各教科の成績状況では、各教科の平均評定と全体の評定平均値が記載されます。
評定平均値は、全科目の成績を合計して科目数で割った数値で、受験生の全体的な学力レベルを表す重要な指標です。
例えば、5教科がそれぞれ「4・5・5・3・3」であれば、合計20となり5で割って評定平均値は4.0です。
多くの大学では推薦入試の出願条件として評定平均値の最低ラインを設定しており、例えば「評定平均4以上」といった基準を満たす必要があります。
一般選抜でも評価の一部として参考情報にされることがあるため、日頃から各教科の学習に真摯に取り組むことが大切です。
成績の総合的な評価
学習成績の概評として、高校3年間の成績を「A〜E」の5段階で総合的に評価した結果が記載されます。
この評価は、以下のように区分されることが一般的です。
- A:5.0〜4.3
- B:4.2〜3.5
- C:3.4〜2.7
- D:2.6〜1.9
- E:1.8以下
この欄には、同じ評価を得た生徒の人数も記載されることがあります。例えば、受験生が「B」評価で、同じ学校で「B」評価の生徒が50人いる場合は「B(50人)」というように表示されます。
これにより、受験校は受験生の成績が同学年内でどの位置にあるのかを把握することが可能です。
「総合的な探究の時間」における活動内容と評価
2022年度から高校教育に導入された「総合的な探究の時間」は、生徒が自ら課題を設定し、解決に向けて探究活動を行う時間です。
調査書にはこの時間における具体的な活動内容と評価が記載されます。
評価は「知識及び技能」「思考力、判断力、表現力等」「学びに向かう力、人間性等」の3つの観点から行われます。
参照:学習指導要領の改訂のポイントと学習評価(高等学校 総合的な探究の時間)
この項目では、例えば「地域の環境問題について調査し、解決策を提案した」「外国語を活用した国際交流プロジェクトを実施した」など、生徒が取り組んだテーマや活動の概要、そして成果が記載されるのが一般的です。
受験校側はこの記録から、受験生の課題発見能力や問題解決能力、そして主体性や協働性といった、これからの時代に求められる力を確認します。
特別活動に関する記録
この項目には、生徒が参加した学校行事や生徒会活動、ホームルーム活動などの特別活動に関する記録が記載されます。
例えば、生徒会長や文化祭実行委員長を務めた場合はリーダーシップや協調性が評価され、体育祭や文化祭での積極的な活動は主体性や行動力が評価されます
特別活動の記録は、単なる参加の有無だけでなく、どのような役割を担い、どのような成果を上げたかという点も大切です。
受験校側は、この記録から受験生の協調性やリーダーシップ、そして社会性を読み取ります。
指導上参考となる事項
この項目には、学業成績以外で受験生をの学校生活などの様々な情報が記載されます。具体的には以下のような内容です。
- 学習における特徴や傾向
- 行動の特徴や特技
- 部活動やボランティア活動、留学経験
- 取得した資格や検定
- 各種表彰や顕彰の記録
- その他参考となる情報
これらの情報は、受験生が高校生活の中でどのような活動に取り組み、どのような成長を遂げたかを具体的に示すものです。
資格取得や部活動での実績は、受験生の努力や能力を客観的に証明するものとして高く評価されます。また、ボランティア活動などの社会貢献活動は、受験生の社会性や倫理観を表す要素として注目されます。
備考欄の記載内容
備考欄は、上記の項目では表現しきれない特別な事情を記載する場所です。
例えば、健康上の理由で長期欠席があった場合など、特別な事情の説明が必要な場合もこの欄に記載されるでしょう。
出欠状況の記録
出欠状況の記録には、各学年における出席すべき日数と、実際の出席日数、そして欠席・遅刻・早退の日数が詳細に記載されます。この記録は、受験生が高校生活にどれだけ真摯に取り組んできたかを示す指標として重要視されます。
特に欠席日数が多い場合は、学校生活への適応能力や健康面での懸念が生じる可能性が高いです。
学校推薦型選抜では、欠席日数の少なさが推薦基準の1つとなっていることが多く、例えば「3年間の欠席日数が10日以内」などの条件が設けられていることもあります。
また、遅刻回数も時間管理能力や規律性の面から評価されるため、「遅刻3回で欠席1日」とカウントする高校もあります。
出欠状況は単なる数字ではなく、受験生の生活習慣や責任感を表す重要な指標として捉えられています。
高校の調査書は大学受験の合否に影響するのか?

総合型選抜や学校推薦型選抜では調査書の中身の情報が合否判定の重要な材料として活用されます。
本人確認や卒業見込み証明書としての役割がメインです。
入試方式ごとの位置づけを理解することで、効果的な受験戦略を立てることができます。
学校推薦型選抜では調査書の評価が重要視される
学校推薦型選抜において、調査書は合否を左右する最も重要な要素の1つです。多くの大学では、評定平均値を出願基準として設定しているほか、公募制では点数化して総合評価に加算します。
一般的な点数化の例として、評定平均値×10倍(50点満点)という方法があり、資格取得や部活動の実績も対象です。
さらに、活動報告書の提出を求める大学では、記載内容について面接で詳しく質問されることもあり、これらの評価が合否に直結する可能性があります。
一般選抜では調査書が合否を左右することはほとんどない
一般選抜では、基本的に学力試験の結果で合否が決まるため、影響することはほとんどありません。
主な用途は以下の通りです。
- 卒業見込証明書としての役割
- 本人確認のための参考資料
- 試験の点数が合格ライン上にある場合の判断材料
ただし、大学によっては調査書を合否判定に活用する場合もあり、募集要項にその旨が明記されています。
通信制高校に通っている生徒の場合は不利になる?
通信制高校に通っている場合でも、調査書は発行されます。
調査書には「通信制課程」の表記がされますが、合否判定が不利になることはありません。調査書の項目は全日制や定時制と同じです。
むしろ、通信制高校を卒業するための努力や自己管理能力は、近年では高く評価される傾向にあります。
ただし、受験対策という観点では、以下の点に注意が必要です。
- 大学受験のサポートが手薄になりがち
- 教師に質問する機会が限られる
- 独学での受験対策が中心となる
高校の調査書は、どうやって入手するの?

調査書は基本的には出願に不可欠な書類であり、確実に入手ことが必要です。調査書を入手するには手続きと時間がかかるため、期限を見据えた早めの行動を取りましょう。
また、出願先の大学の数に応じて必要枚数も変わるため、その点も考慮して準備を進める必要があります。
以下では、調査書の入手方法の具体的な方法と注意点について解説します。
調査書の入手方法
調査書を入手するには、高校が定める「調査書発行願」などの申請書類を記入し、担任の先生または進路指導室に提出しなければなりません。
多くの高校では、申請書に保護者の署名・捺印を求められるため、事前に書類を確認しておくことが大切です。
申請後は学校で直接受け取るか、郵送で届けられるのが一般的な入手方法です。高校によって発行手続きや費用は異なり、私立高校では300〜500円程度の費用がかかる場合もあります。
在校生は担任の先生や進路指導の先生に、卒業生は母校の事務局に調査書の入手方法を確認すると良いでしょう。
発行申請は余裕を持って早めに行う
調査書をスムーズに入手するためには、発行までに約2週間程度かかることを想定しておきましょう。
特に出願シーズンの12月末〜1月末は、多くの生徒が同時期に調査書を必要とするため、学校の事務局は非常に忙しくなっています。
また、12月3週目から1月1週目にかけては冬休みで対応できない学校も多いため、12月2週目までに発行依頼をするのが安心です。
調査書は発行日から3ヶ月間有効ですので、早めに必要枚数を揃えておけば、出願期間中の余計な心配を減らせます。出願締切に慌てることのないよう、余裕を持った入手方法を心がけましょう。
出願する大学ごとに1通ずつ必要になる
基本的に調査書は1回の出願につき1通必要です。
例えば、同じ大学の前期日程と系統別日程を同時に出願する場合は、インターネット出願で一括申請できるため1通で構いません。
ただし、複数の大学を受験する場合は、それぞれの大学に1通ずつ提出する必要があったり、共通テスト利用入試を併願する場合や後期日程を受験する場合は出願時期が異なったりするため、別途調査書が必要になる場合があります。
各大学の募集要項を事前に確認し、必要な調査書の枚数を正確に把握しておくようにしましょう。
2025年度入試では高校の調査書の何が変わる?

2025年度入試から、調査書の様式が大きく変更されることをご存知でしょうか。新学習指導要領の導入に伴い、以下3項目で重要な変更が加えられます。
- 総合的な探究の時間
- 特別活動
- 指導上参考となる諸事項
ここでは、2025年度入試から変わる調査書の主な変更点を詳しく解説します。
「総合的な探究の時間」の評価が3つの観点から行われる
2025年度入試から、「総合的な探究の時間」の記載方法が大きく変わります。
- 「知識及び技能」「思考力、判断力、表現力等」「学びに向かう力、人間性等」の3つの観点での評価が記載される
- 2024年度までは、探究活動のテーマや内容だけが記載されていた
- 学習活動、観点、評価の3要素が明確に記入される様式に変更
これまで、探究活動のみ内容が記載されていましたが、新しい様式では3つの観点での評価まで含まれるようになりました。
これにより、受験校側は生徒の学びの過程や取り組み方をより具体的に把握できるようになり、学校推薦型選抜などの合否判定に活用される可能性が高まります。
部活動の実績や取得資格などは別紙で詳しく記録される
「指導上参考となる諸事項」についての記載方法にも変更がありました。
- 2024年度までの6項目の詳細な記載から、1つの記載欄に集約される
- 部活動の成績や取得資格などは別紙の活動報告書に詳述される
- 一般選抜では「特記事項なし」と記載されるケースが増える可能性がある
これまで調査書に詳細に記載されていた部活動の成績や取得資格などの情報は、別紙の活動報告書に詳しく記入されます。
この変更により、調査書は一般選抜ではシンプルになる一方、学校推薦型選抜などの方式では活動報告書がより重要な役割を持ちます。
高校の調査書とは?|まとめ

高校の調査書は、大学受験における重要な書類として入試方式ごとに異なる役割を果たします。
調査書には、高校の生活や学習における姿勢などが事細かに記載されています。学校推薦型選抜などでは合否判定の主要な材料となります。
さらに、2025年度入試からは調査書の様式が変更されるため、早めに情報を把握し、計画的に準備を進めることが求められます。
受験生の皆さんは、自分の受験方式に合わせて調査書の重要性を理解し、必要な対策をしっかり取るようにしましょう。
おすすめコラム