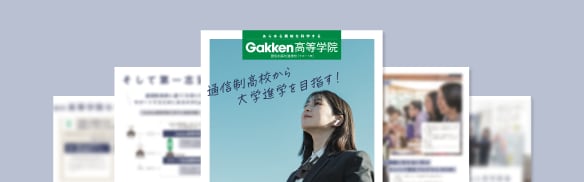併願とは?中学・高校・大学受験で知っておくべき受験方式を解説
2025.07.21

-
進学・進路でお悩みの方
-
授業料・詳細を知りたい方

「併願」は、受験における重要な戦略の一つです。
しかし、「そもそも併願とは何か」「どの入試方式で併願できるのか」といった基本的な疑問を持つ方も少なくありません。
この記事では、中学・高校・大学受験における併願の仕組みから具体的な選び方まで詳しく解説します。
併願とはどんな制度?基本的な仕組みを解説

併願とは、複数の学校を受験する方式のことです。
複数の学校から合格を得たうえで、進学先を自分で選べる点が大きな特徴です。
例えば、第一志望の公立高校に加えて、万が一の場合に備えて私立高校も受験するケースなどが併願にあたります。
専願(単願)とは?併願との違いとは?
併願とは対照的に、専願は基本的に1校のみの出願となり、合格したら必ずその学校に入学することを約束する受験方式です。
学校側にとって入学者確保のメリットがあるため、併願に比べて合格ラインが下がったり試験科目が少なかったりなどの優遇措置が取られる場合もあります。
大学受験での併願とは?併願できない試験方式について

大学受験は入試方式が多様化しており、それぞれ併願に関するルールが異なります。
知らずにルール違反をしてしまうと、合格が取り消される可能性もあるため、必ず募集要項で確認しましょう。
学校推薦型選抜や指定校推薦は専願が条件
学校推薦型選抜は、指定校推薦と公募推薦の2種類があります。
指定校推薦は、大学が指定した高校に対して枠を設けて行う推薦方式で、合格後の入学が必須となる「専願」が前提となります。
一方、公募推薦は全国の高校から条件を満たせば誰でも出願できる方式で、大学によっては「併願可」としている場合もあります。
ただし、「第一志望であること」や「合格した場合は進学する意志があること」が求められるケースもあり、実質的に専願に近い扱いとなることもあるため注意が必要です。
また、学校推薦型選抜では評定平均(例:3.8以上など)が出願条件に設定されていることが多く、学業成績が重視されます。
試験日程も一般選抜より早く、合格後の手続き期限も早めに設定されているため、他の入試方式との併願計画を立てる際は十分な確認が必要です。
総合型選抜(旧AO入試)は併願できない場合もある
総合型選抜は、大学側が求める学生像と受験生のマッチングを重視する入試です。
近年、総合型選抜を実施する大学の8割程度が併願を認めており、受験生の選択肢は広がっています。
ただし、東京大学の学校推薦型選抜や一部の医学部など、専願を条件とする大学もあるため、志望校の募集要項は必ず確認が必要です。
募集要項に「専願制」や「併願禁止」といった記載がなければ、原則として併願可能と考えて良いでしょう。
| 併願が可能な場合の特徴 ・募集要項に併願に関する制限の記載がない ・「併願可」と明記されている ・合格後でも一定期間内であれば進学を辞退できる |
| 専願が条件となる場合 ・募集要項に「専願制」「併願禁止」の記載がある ・「本学を第一志望とする者」という条件がある ・「合格したら必ず入学すること」が出願条件となっている |
公募推薦は併願不可の場合もある
公募推薦は、大学が定める条件を満たせばどの高校からでも出願できる推薦入試で、専願の場合と併願可能な場合があります。
専願か併願かは、各大学の「募集要項」で確認できます。
例えば、国公立大学の学校推薦型選抜への出願は『一つの大学・学部』に限られており、ある国公立大学の学校推薦型選抜に出願した場合、別の国公立大学の学校推薦型選抜に出願することはできません。
一方、国公立大学の総合型選抜については、国立大学協会では併願の可否について一律に定めておらず、各大学の方針により異なります。
高校受験での併願とは?併願できない試験方式について

高校受験では、基本的に併願は可能ですが、一部の入試方式や条件で併願が制限される場合があります。
ここでは、高校受験で併願ができない具体的なケースについて詳しく解説します。
高校推薦入試は多くが併願できない
高校の推薦入試は、多くの場合で専願が条件となっているため、併願での受験ができないことが多いです。
推薦入試では中学校長の推薦書が必要で、学業成績や部活動実績、特別活動などが総合的に評価されます。
多くの私立高校では推薦入試が専願制となっていますが、地域によっては併願推薦制度(東京都の併願優遇制度など)があるため、各都道府県の制度を確認することが大切です。
推薦入試は一般入試と比較して合格基準が優遇される場合が多く、面接や作文が重視される傾向があります。
公立高校の自己推薦型入試も専願が基本
公立高校には「自己推薦型入試」と呼ばれる入試方式があり、これも専願が条件となります。
自治体によって「前期選抜」「特色入試」「特別選抜」などの名称で実施されており、1月下旬から2月にかけて行われることが一般的です。
この入試では面接を中心に、中学校時代の活動実績や志望動機などが評価されます。
合格した場合は必ずその高校に入学する必要があるため、他の専願入試との併願はできません。
私立高校の専願入試も併願はできない
私立高校では推薦入試とは別に「専願入試」を設けている学校もあります。
これは一般入試の一種ですが、合格したら必ず入学することを条件とした入試方式です。
12月頃から早期に実施されることが多く、併願入試よりも合格基準が優遇される傾向があります。
中学受験での併願とは?併願できない試験方式について

中学受験では、多くの学校で併願が可能ですが、一部の入試方式や条件で併願が制限される場合があります。
中学受験で万が一不合格となってしまった場合には、市町村で決められた公立中学校に進学することとなります。
中学の推薦入試は多くが併願できない
中学受験において「推薦入試」という形式は少数ですが、一部の中学校では推薦書や活動実績の提出を求める、専願制の入試を設けている中学校もあります。
中学校の推薦入試は、基本的に「専願」が条件となりますので併願での受験ができないことが多いです。
合格したら必ずその中学校に入学することを約束して出願するため、他の中学校との併願はできません。
推薦入試を受験する場合は、その学校を第一志望として確実に入学する意志が必要となります。
併願受験で知っておくべき注意点

併願受験を行う際には、事前に知っておくべき注意点があります。
これらの注意点を把握せずに受験すると思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があるため、必ず確認しておきましょう。
入試日程の重複に注意が必要になる
同じ日時に複数の学校を受験することはできません。
特に人気校同士が同じ日程で入試を行う場合、どちらか一方しか受験できないため、事実上の併願制限となります。
事前に試験日を確認し、志望する学校の試験日を踏まえて、併願校として選択できるかを確認する必要があります。
高校受験の試験日の傾向
高校受験では都道府県立高校の入試日が統一されていることが多く、複数の公立高校を同日に受験することはできません。
ただし、隣接する都道府県の公立高校であれば、日程次第で併願が可能なこともあります。
中学受験の試験日の傾向
中学受験では、首都圏では2月1日〜3日に試験が集中するため、複数校を併願する際は日程調整が重要です。
関西圏では統一入試日が設けられているため、事前に受験校の優先順位を決めておく必要があります。
午前・午後入試を活用して同日に複数校受験する戦略もありますが、小学6年生の体力的な負担を考慮すると得策とは言えません。
学費の負担を事前に計算する
併願校を選ぶ際は、受験料だけでなく入学後の学費についても事前に計算しておくことが重要です。
私立学校の場合、入学金、授業料、施設費、制服代などを含めると年間で数十万円から百万円以上の費用がかかる場合があります。
特に複数校から合格をもらった場合、入学金の支払い期限が重なることもあるため、家計への負担を十分に検討しておく必要があります。
奨学金制度や特待生制度がある学校もありますので、経済的な支援についても併せて調べておきましょう。
合格手続きの締切日に注意
合格後は、手続き締切日までに手付金を納入する必要があります。
併願する学校の合格発表日と手続き締切日の関係を必ず確認しておきましょう。
第一志望校の合格発表前に併願校の入学金を支払う必要がある場合、経済的な負担が大きくなることも考慮が必要です。
国公立大学と私立大学の入試制度における注意点
国公立大学の場合は併願数が限られるため、志望校選びは慎重に行う必要があります。
前期で難関校に挑戦し、中期・後期で確実に合格できる大学を選ぶなど、戦略的な併願計画が重要です。
私立大学の場合なら受験校数に制限がない分、受験料や交通費、宿泊費などの経済的負担が膨らみやすくなります。
また、受験日程が重複しないよう事前のスケジュール調整も欠かさないようにしましょう。
併願とは?に関するよくある質問(Q&A)

ここでは、併願とはどんな受験方法なのか?を調べている多くの受験生や保護者の方が抱く疑問について、Q&A形式でお答えします。
併願を検討する際によく聞かれる質問をまとめましたので、受験計画の参考にしてみてください。
Q1.併願では何校まで受験できる?
制度上、併願できる学校数に明確な上限はありません。
しかし、受験校が増えればそれだけ受験料の負担が増え、試験対策や体調管理も大変になります。
一般的な目安として、大学受験では3~7校、高校受験では2~3校、中学受験では5~7校程度を検討する方が多いです。
Q2.併願校に優遇措置はある?
併願校でも、学校によっては優遇措置が設けられている場合があります。
例えば、高校受験の「併願優遇」制度や、内申点による優遇などがこれにあたります。
ただし、これらの制度は学校や地域によって大きく異なるため、志望校の募集要項や説明会で詳細を確認することが重要です。
Q3.併願校の入学を辞退したら、支払った入学金は返ってくる?
一度支払った「入学金」は、入学を辞退しても返還されないのが原則です。
これは「入学できる権利」を得るための費用と見なされるためです。
ただし、入学金と同時に支払った「授業料」などについては、指定された期日までに入学辞退の意思表示をすれば返還される場合がありますので、各学校の規定をしっかり確認しましょう。
Q4.通信制高校も全日制と併願できる?
通信制高校も全日制高校や定時制高校と併願することが可能です。
多くの通信制高校は、学力試験ではなく書類選考や面接で合否が決まるため、全日制高校の受験勉強と両立しやすいという特徴があります。
全日制高校を第一志望としながら、進路の選択肢を広げるために通信制高校を併願するケースが増えています。
通信制高校は、自分のペースで学べる柔軟な学習スタイルが特徴で、全日制以外の進路を検討する際の有力な選択肢です。
Q5.同じ学校でも複数回受験できる?
多くの学校で複数回の受験機会を設けています。
特に私立大学では、一般選抜を複数日程で実施したり、共通テスト利用入試と一般選抜の両方を受験したりすることが可能です。
同一校を複数回受験する場合、受験料の割引制度を設けている学校も多いため、積極的に活用しましょう。
まとめ│併願とは?中学・高校・大学受験で知っておくべき受験方式を解説
併願とは何かを正しく理解することで合格のチャンスを広げ、安心して第一志望に挑戦するための重要な戦略となります。
中学・高校・大学受験それぞれで異なるルールがあるため、事前の確認が欠かせません。
むやみに数を増やすのではなく、学力や目的、体力・費用面も考慮しながら、計画的に併願校を選ぶことが大切です。
併願の仕組みを理解し、この記事を参考にしながら、自分に合った受験プランで合格を目指してみてください。
おすすめコラム