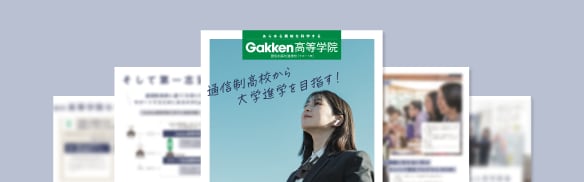高校の定期テストの勉強法を解説!始める時期やコツは?
2025.10.10

-
進学・進路でお悩みの方
-
授業料・詳細を知りたい方

高校生活における定期テストは、日々の学習の成果を確認する重要な機会であり、成績や進路にも直結します。
しかし、効率的な勉強法が分からず、テスト前に不安や焦りを感じる高校生も少なくありません。
そうした状況を避けるためには、勉強を始める時期や教科ごとの学習のコツを把握し、計画的に取り組むことが欠かせません。
この記事では、定期テストで成果を上げたい高校生に向けて、勉強を始めるべき時期や5教科別の学習法、さらに高得点を目指すための実践的なコツを解説します。
定期テストの勉強を始めるべき時期は?
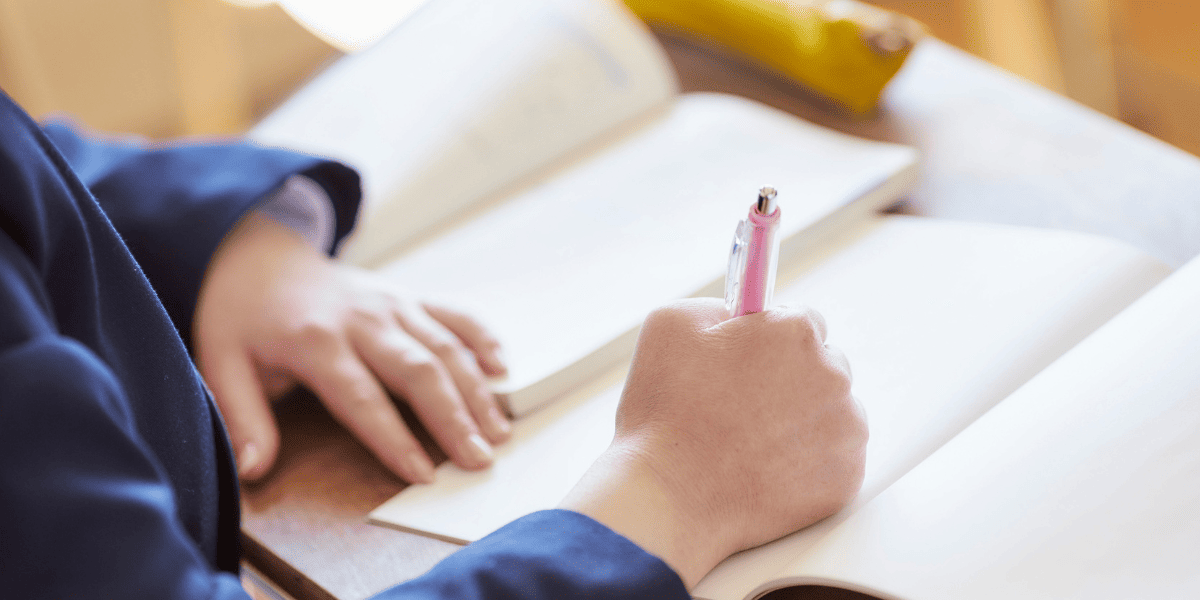
定期テストは、直前に慌てて取り組むのではなく、余裕をもって準備を進めることが大切です。
中間テストと期末テストでは範囲や特徴が異なるため、それぞれに合わせて開始時期を工夫する必要があります。
多くの高校では、学期の前半に中間テスト、学期末に期末テストが実施されます。
中間テストは範囲が比較的狭い一方で準備期間が短いため、少なくとも2週間前から学習を始めるのが理想です。
一方、期末テストは範囲が広いため、3週間前を目安に計画的に進めると安心です。
日頃から授業内容を復習しておくことで、テスト直前は総仕上げに集中でき、精神的にも余裕を持って取り組めます。
英語の定期テスト勉強法

高校英語は積み重ねが不可欠な教科であり、本文理解や単語学習を軸に据えながら、文法やリスニングもバランスよく学習していくことが求められます。
効率よく知識を整理し、実際のテストで使える形にすることを意識しましょう。
教科書の本文理解と単語暗記
英語の定期テストでは教科書本文からの出題が多いため、繰り返し音読して内容を正確に理解するようにしましょう。
本文中の単語や熟語は、例文とあわせて覚えることで知識が定着し、英作文や読解にも応用できます。
文法や構文の理解
文法や構文は、英文を正しく読み解くための基礎です。
授業で習った項目を整理し、不安な部分は解説や例文で確認しましょう。
さらに、実際に問題を解いてアウトプットすることで、覚えた知識を「使える力」へと変換できます。
リスニング対策
リスニングは短期間で成果を出すのが難しいため、毎日の積み重ねが重要です。
音声を繰り返し聞くことで、発音やリズムに慣れ、英語を自然に聞き取れる耳を育てられます。
耳からの理解力が向上すると、リーディングやライティングにも良い影響を与え、英語力全体の底上げにつながります。
数学の定期テスト勉強法
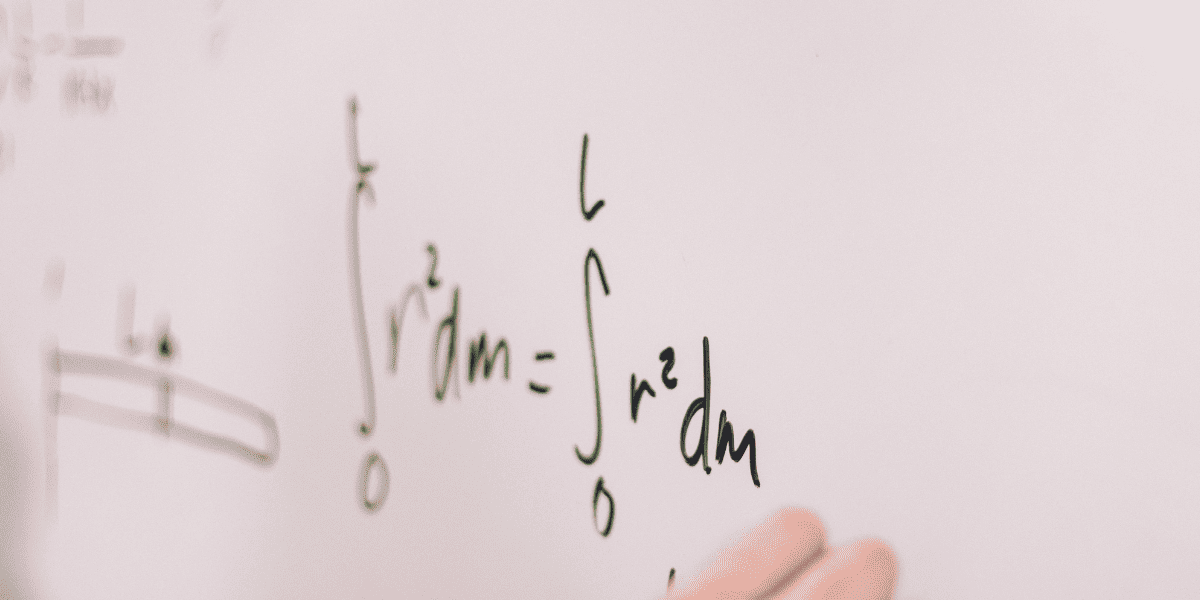
数学は基礎を固め、その上で応用力を鍛えることが大切な教科です。
理解と演習を繰り返しながら、知識を定着させていく学習スタイルを意識しましょう。
解き直しを徹底する
間違えた問題は放置せず、必ず解き直すことが理解を深める鍵になります。
解き直しをすることで、自分がどこでつまずいたのかを理解し、弱点を確実に克服できます。
また、解き直した内容をノートにまとめておくと、直前期の見直しにも役立ち効率的な学習につながります。
公式を使う場面を理解する
公式はただ暗記するだけでなく、どのような場面で活用できるのかを理解して初めて使いこなせるようになります。
例題や演習問題を通じて「この問題にはこの公式を使う」と関連付けて学ぶことで、実戦で迷わず活用できます。
公式を正しく使えるようになれば、解答スピードも安定し自信を持って問題に取り組めるでしょう。
応用問題に取り組む
高得点には応用問題が欠かせませんが、その前に計算問題など基礎を確実に固めましょう。
基礎から応用へ段階的に進めることで、負担を減らし自然に得点力を高められます。
国語の定期テスト勉強法
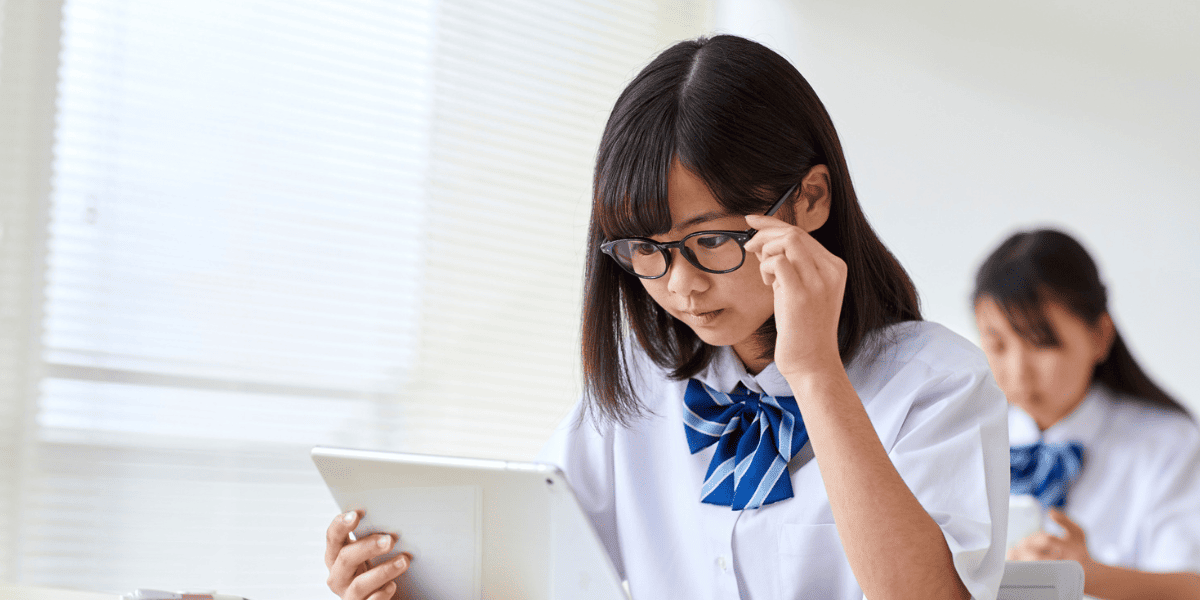
国語は現代文・古典・漢字など幅広い分野を含んでおり、それぞれの特性に合わせて学習を進める必要があります。
分野ごとに重点を意識して学ぶことで、安定した得点を狙えるようになります。
現代文は本文読解を中心に
現代文では、文章を丁寧に読み、設問の意図を正確に理解する力が問われます。
段落ごとに要点を整理しながら読んだり、自分の言葉で要約する練習をすることで、内容を正確に把握でき、記述問題にも対応しやすくなります。
古典の文法・単語整理
古典では、助動詞や敬語などの文法事項を表でまとめて繰り返し確認するのが効果的です。
助動詞や敬語の用法を表にまとめて繰り返しインプットとアウトプットをすることで、効率よく学ぶことができ、テストでも高得点が期待できます。
古典単語も、例文とあわせて覚えると実際の読解でも使える知識になります。
漢字・語彙の強化
漢字や語彙は努力が点数に直結する分野です。
毎日少しずつ練習を積み重ね、テスト範囲を中心に反復して確認することが大切です。
熟語や類義語・対義語なども関連付けて学ぶと、理解が深まり、他教科の読解にも好影響を与えます。
理科の定期テスト勉強法
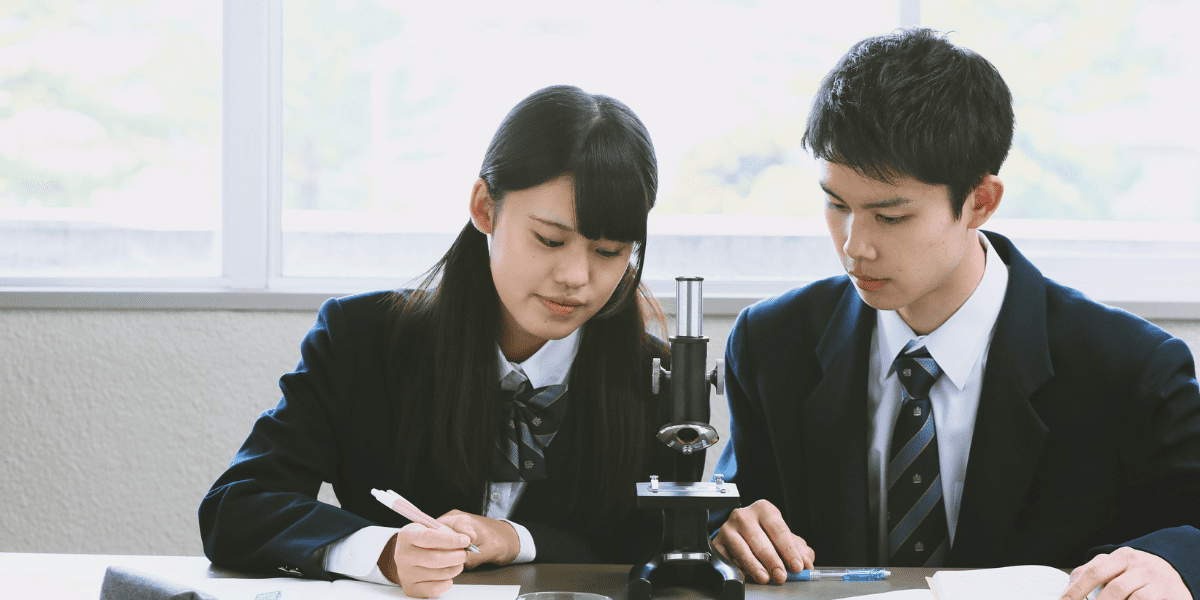
理科は暗記と理解の両方が求められるため、図や実験を活用した学習法を取り入れると知識が定着しやすくなります。
体系的に整理して学ぶことで、複雑な内容も整理して理解できるようになります。
図や表を活用して理解する
単元や分野によりますが、理科は文章だけで覚えるよりも、図や表を用いて情報を整理しましょう。
自分で図を描きながら説明できるようにすると、知識が「使えるもの」へと変化します。
また、ビジュアルを活用した学習は記憶にも残りやすいという利点があります。
実験内容をおさえる
実験の手順や結果は定期テストでの頻出テーマです。
授業で扱った実験の目的・方法を元に、そこから得られた結論を整理することで得点につながります。
加えて、器具の名称や役割を確認しておくと、記述問題で差をつけることができます。
演習を通して用語を定着させる
理科では正確な用語の理解が不可欠です。
正しく理解していないと誤った知識のまま進めることになってしまいます。
教科書や問題集を繰り返し解いてアウトプットすることで、自然に記憶が定着していきます。
暗記した知識を演習問題で確かめることで、実際の問題にも対応できるようになるでしょう。
社会の定期テスト勉強法

社会は覚える量が多い一方、理解を深めれば長期的に知識が残りやすい教科です。
資料や問題演習を活用しながら、多角的に学ぶ姿勢を持つことが効果的です。
流れで理解する
歴史や政治経済を学ぶ際は、単語や出来事を丸暗記するのではなく、因果関係や背景を意識した学習が効果的です。
また、時系列を意識して整理することで関連付けて思い出しやすくなり、試験でも安定して得点できるようになるでしょう。
資料を使った確認
社会科目では、地図やグラフ、統計資料などを読み取る力も必要です。
授業で使用した資料集やプリントを使って復習し、資料を見て理解するだけでなく、自分の言葉で説明できる状態にすることを目指しましょう。
また、実際の問題形式に慣れておくことで、試験本番に自信を持って臨めます。
問題演習で知識を定着
社会科目は演習を通じて知識を実際に使える形にすることが大切です。
演習を重ねることで、自分の知識がどこまで通用するのかを確認できます。
間違えた箇所を復習し、弱点を重点的に補強していくと安定した得点につながります。
定期テストで高得点を取る3つのコツ

定期テストで成果を上げるためには、日々の授業や学習の積み重ねに工夫を加えることが必要です。
ここでは特に効果的な3つのポイントを紹介します。
毎日の授業を復習する
授業内容をその日のうちに振り返る習慣をつけると、理解が浅い部分を早めに補うことができます。
日々の復習を積み重ねることで知識が確実に定着し、テスト前に慌てる必要が無くなります。
また、授業と復習を結びつける習慣は、長期的な学力向上にもつながります。
優先順位を決めて学習する
すべての範囲を完璧に仕上げることは難しいため、配点が高い単元や苦手分野から取り組むことで効率的に学習を進められます。
優先順位を意識すれば学習の計画性が養われます。
その結果、限られた時間でも成果につなげやすくなります。
演習と確認を繰り返す
高校の定期テストの勉強はインプットしただけでは不十分です。
実際に問題を解いてアウトプットし、理解の浅い箇所を修正することで初めて実力が身につきます。
インプットとアウトプットのサイクルを繰り返すことが最も効率的な得点アップのための勉強方法です。
高校の定期テストの勉強法と始める時期やコツ|まとめ
高校の定期テストは、始める時期を意識し、教科ごとの特性に合わせた学習法を実践することで結果が大きく変わります。
また、授業内容を日々復習し、優先順位を立てて計画的に学習を進めることで効率的な準備が可能になります。
演習と確認を繰り返すことで知識が確実に定着し、本番でも自信を持って臨めるようになります。
計画的な学習を習慣化すれば、不安を解消し安定して高得点を目指せるでしょう。
おすすめコラム