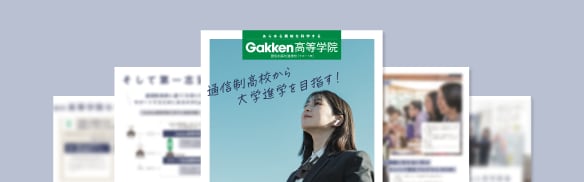総合選抜型とは?メリットや対策・受かりやすい大学もご紹介
2025.05.21

-
進学・進路でお悩みの方
-
授業料・詳細を知りたい方

総合型選抜とは、大学受験の入試方式の一つで、2021年にAO入試から再定義されました。
この記事では、総合型選抜とは具体的にどのような入試制度なのか、一般選抜や学校推薦型選抜との違いは何かを詳しく解説していきます。
メリット・デメリットを踏まえつつ、合格に向けた対策や、自分に合った受かりやすい大学選びのヒントもご紹介していきます。
総合型選抜とは?どのような入試方式なのか?
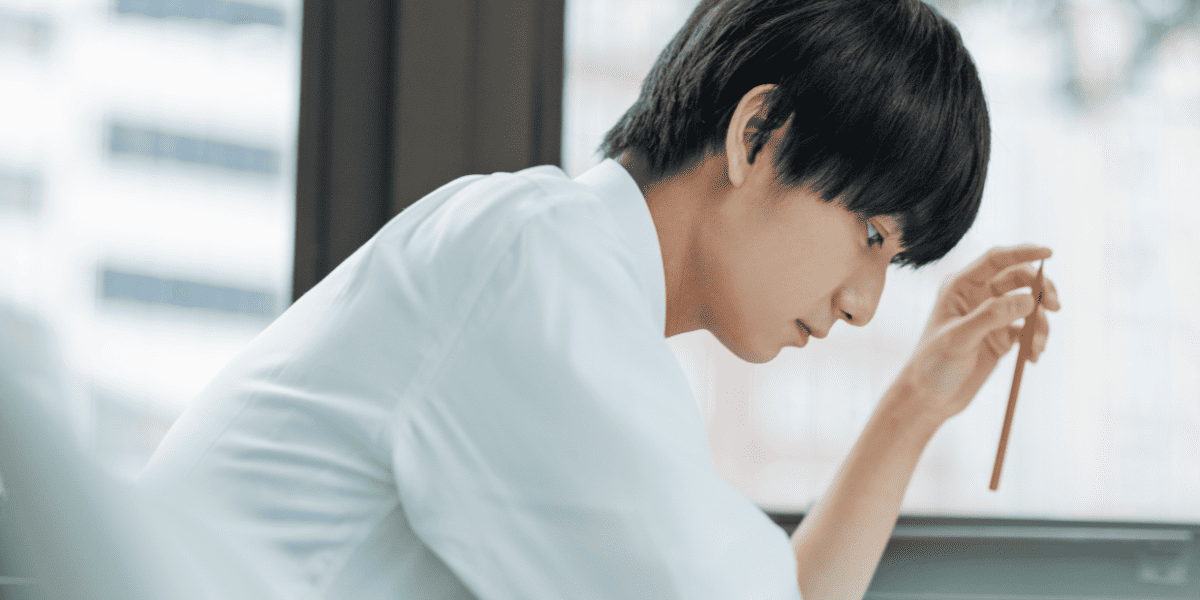
総合型選抜とは、従来の学力試験中心の入試とは異なり、出願書類(志望理由書や活動報告書など)、小論文、面接、プレゼンテーションなどを通して、受験生の能力・適性や学習意欲、将来性などを総合的に評価する入試方式です。
以前は「AO入試(アドミッションズ・オフィス入試)」と呼ばれていましたが、2021年度入試から名称が変更されました。
評価の際には、文部科学省が示す「学力の三要素」が重視されます。
- 知識、技能
- 思考力、判断力
- 主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度
つまり、総合型選抜とは学力だけでは測れない個性や経験、意欲を持つ受験生にとって、大きなチャンスとなる入試方式と言えます。
総合型選抜とは?一般選抜の評価方法の違いについて
総合型選抜と一般選抜との最も大きな違いは、評価の方法にあります。
一般選抜が主に学力試験(大学入学共通テストや大学独自の試験)の成績で合否を判断するのに対し、総合型選抜とは書類審査や面接、小論文など、より多角的な視点から評価する入試方式です。
また、出願・選考時期も異なり、一般選抜は1月~3月が中心ですが、総合型選抜は9月~11月頃と比較的早く始まります。
総合型選抜では、学力に加えて人間性や将来への意欲なども評価されるため、多様なバックグラウンドを持つ生徒にも門戸が開かれています。
総合型選抜とは?学校推薦型選抜との違い
学校推薦型選抜(旧 推薦入試)との主な違いは、出身高校長の推薦が必要かどうかという点です。
学校推薦型選抜では出身校の校長推薦が必須ですが、総合型選抜は原則として自己推薦で出願できます。
学校推薦型選抜、特に指定校推薦では高校での成績(評定平均)が非常に重視されますが、総合型選抜では評定平均も考慮されるものの、それ以上に大学が求める人物像(アドミッション・ポリシー)との適合性や、活動実績、学習意欲などが総合的に評価される傾向にあります。
総合型選抜とは、主体的に挑戦しやすい入試方式であるため、特に指定校推薦の枠が少ない、あるいは利用しにくい環境にある通信制高校の生徒にとっても大きなメリットがあります。
総合型選抜のメリットとデメリット

総合型選抜とは、受験生にとって多くの魅力がある一方で、注意すべき点も存在します。
総合型選抜のメリットとデメリットを正しく理解し、「対策」を考える上で参考にしてください。
学力試験以外の強みを活かせる|メリット
総合型選抜の大きなメリットの一つは、学業成績だけでは測れない多様な側面を評価してもらえる点です。
例えば、部活動でのリーダーシップや継続的な努力、ボランティア活動を通じた社会貢献への意識、あるいは独自のテーマで取り組んだ探究活動の成果などもアピール出来るポイントになり得ます。
総合型選抜とは、受験生一人ひとりの個性やユニークな経験、そして試験だけでは見えにくい潜在的な能力を大学にしっかりと伝えることが出来れば、それが自分の「強み」となる入試方式といえます。
早期に合否が決まる可能性がある|メリット
総合型選抜では、多くの大学で年内に合否が発表されるケースが一般的です。
早い段階で進路を確定できるため、受験勉強のプレッシャーから早期に解放され、精神的にも負担は少ない場合が多いです。
例えば、大学での学びに向けた準備期間として専門分野の基礎学習に取り組んだり、興味のある分野の探究を深めたりするなど、自己成長のための貴重な時間を確保することができます。
受験機会が増え、進路選択の幅が広がる|メリット
総合型選抜では、進路選択の幅を広げることが出来るメリットも持っています。
万が一、総合型選抜で思うような結果が得られなかったとしても、同じ大学の一般選抜に再度挑戦できる場合が少なくありません。
さらに、大学によっては他の入試方式との併願が認められていることもあり、複数の大学や学部を視野に入れた受験戦略を立てることが可能です。
ただし、併願の可否や条件は大学や学部によって大きく異なるため、必ず出願前に募集要項を隅々まで確認し、正確な情報を把握しておくことが重要です。
対策に時間と労力がかかる|デメリット
総合型選抜のデメリットとして、対策に時間や労力がかかるというものが挙げられます。
自己分析や大学・学部研究、志望理由書をはじめとする書類作成、さらには面接や小論文の対策など、多岐にわたる項目が含まれ、これらは一朝一夕にできるものではなく、高校の早い段階、例えば高校2年生など早い段階からの計画的な取り組みが求められます。
さらに学力以外の強みを活かせるということは、これまでの積み重ねを評価されるということでもあるので、思い立ってすぐに対策が出来るというものではありません。
ですので、総合型選抜での受験は早期に計画を立てることが重要だと言えます。
合格に明確な基準がない|デメリット
総合型選抜では、提出書類の内容や面接での応答、態度などが評価の対象となります。
これらの評価には、面接官の印象や書類の解釈といった主観的な要素が影響する可能性があり、学力試験のように明確な基準だけで合否を予測することが難しい側面があります。
この不確実性は、受験生にとって不安要素となるかもしれません。
ただし、近年では多くの大学で評価基準の明確化を図ったり、一部で学力を測る要素を導入したりするなど、評価の客観性を高めるための取り組みが進んでいます。
一般選抜との両立が大変|デメリット
総合型選抜と一般選抜では、評価される能力や求められる対策が大きく異なることもデメリットになり得ます。
このため、両方の選抜方式での合格を目指す場合、それぞれに特化した対策が必要となり、学習時間や精神的な負担が増加する可能性があります。
そのため一般選抜と総合型選抜の両立を考えると、それなりの負担を感じるかもしれません。
総合型選抜で受かりやすい大学とは?カギは「相性の良いマッチング」

総合型選抜は、「受かりやすい大学を見つけるための入試」と考える方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、総合型選抜で本当に大切なのは、一般的な意味での「受かりやすさ」ではなく、 あなたと大学との相性の良いマッチング。
これこそが、結果的にあなたにとっての「受かりやすい大学」を見つけるカギとなります。
総合型選抜の「受かりやすさ」は"相性"で決まる
総合型選抜で受かりやすい大学は、一般選抜とは違って偏差値で決まるものではありません。
むしろ、大学が掲げる「アドミッション・ポリシー(入学者受け入れの方針)」と、自分の個性、強み、学びたいこと、将来の目標がどれだけ合致しているかが重要です。
さらに言うならば「自分の持つポテンシャルや経験を最も高く評価してくれる大学」こそが、自分にとっての「受かりやすい大学」と言えるかもしれません。
総合型選抜ではアドミッション・ポリシーを読み解くことが最初の対策
各大学・学部のアドミッション・ポリシーには、「どのような学生を求めているか」「入学までにどのような力を身につけておいてほしいか」が具体的に示されています。
これを徹底的に読み込み、理解することが、合格に向けた最も重要な対策だといっても良いでしょう。
自分の経験と大学の特徴を結びつける
大学のウェブサイトやパンフレット、オープンキャンパスなどを通じて、カリキュラムの特色、教員の研究内容、在学生の活動などを調べてみてください。
そして、自分のこれまでの経験や活動、興味関心が、その大学の学びや特色とどのように結びつくのかを具体的に考えてみましょう。
例えば、「地域貢献活動に力を入れている学部」に対して、「高校時代に地域ボランティアに熱心に取り組んだ経験」があれば、それは強力なアピールポイントになります。
自分の「強み」を軸にした大学選び
倍率や偏差値だけで判断するのではなく、「自分の学びたいこと、自分の個性を最も活かせる大学はどこか」という視点で大学を探すことが、総合型選抜における受かりやすい大学を見つける最良の方法です。
この「マッチング」を意識した大学選びこそが、合格への近道なのです。
総合型選抜で合格をつかむための具体的対策

総合型選抜とは、いうなれば「付け焼き刃の対策では通用しない、準備の質と量が合否を左右する入試」です。
ただ漠然と「ありのままの自分でぶつかっていけば良いんだ」ということはありません。
また、「総合型選抜=学力が必要ない受験」だと思っている人も注意が必要です。
戦略的に取り組むことが重要です。
早めの対策スタートが重要
総合型選抜の準備は、高校3年生になって対策をスタートするのではなく、より早いタイミングから、総合型選抜での受験を見据えた準備を始めるのが理想です。
ボランティア活動や学びたい分野に対する探究のような活動実績は短期間では作れません。
また、なぜその大学で学びたいのか?という志望理由の熟成にも期間は必要になります。
自己分析と志望理由の深掘り
「なぜこの大学・学部で学びたいのか」「将来何をしたいのか」といった問いに、自身の経験と結びつけて具体的な答えを用意する必要があります。
過去の経験を棚卸しし、そこから得た学びや価値観を言語化しましょう。
これが志望理由書や面接の核となります。
説得力のある志望理由書の作成
志望理由書は、自分の経験・強み・学びたいこと・将来の目標と、大学のアドミッション・ポリシーを結びつけ、一貫性のあるストーリーとして記述します。
志望理由書の具体的な構成例:
導入:自分が志望学部の学問分野に興味を持ったきっかけや、大学で学びたい内容の概要
↓
本論①:自分のこれまでの経験や取り組み(具体的なエピソードを交えて)
本論②:志望大学・学部の特色と自分の目指すものとの関連性
本論③:入学後の具体的な学習計画や研究テーマ
↓
結論:大学での学びを通じて実現したい将来像や社会貢献
というように、論理的で熱意の伝わる文章を目指しましょう。
単なる憧れではなく、具体的な根拠を示すことが重要です。
その他、抽象的な表現を避け、「〜に興味があります」ではなく「〜という講義で〜について学び、〜という課題に取り組みたいです」など具体的に記述をすることも大切です。
また、自身で作成した志望理由書は、かならず誰かに添削を依頼しましょう。
学校の先生や塾の講師など第三者に読んでもらい、客観的な視点からのフィードバックを得ることが非常に重要です。
面接対策:対話力と熱意を伝える
面接では、自分の考えを明確に話す力に加え、質問の意図を理解し、対話する姿勢が求められます。
また志望理由書をもとにした質問が多く予想されるので、想定される質問への回答を準備するだけでなく、模擬面接を繰り返し行い、自信を持って自分の言葉で話せるように練習しましょう。
特に通信制高校生は対話形式の練習機会が少ない場合もあるため、積極的に外部のサポートを活用することをおすすめします。
小論文・プレゼンテーション等への備え
大学によっては、小論文、プレゼンテーション、グループディスカッションなどが課されます。
募集要項で選考内容を確認し、それぞれの形式に合わせた対策を行いましょう。
小論文は実際に書いて添削を受ける、プレゼンは時間を計って発表練習をする など、実践的な練習が不可欠です。
活動実績の整理と記録
高校時代の活動(部活動、ボランティア、資格取得、探究学習など)について、具体的な内容、成果、そこから学んだことなどを整理し、記録しておきましょう。
ポートフォリオとしてまとめておくと、書類作成や面接時に役立ちます。
通信制高校生にも有利?総合型選抜の活用法
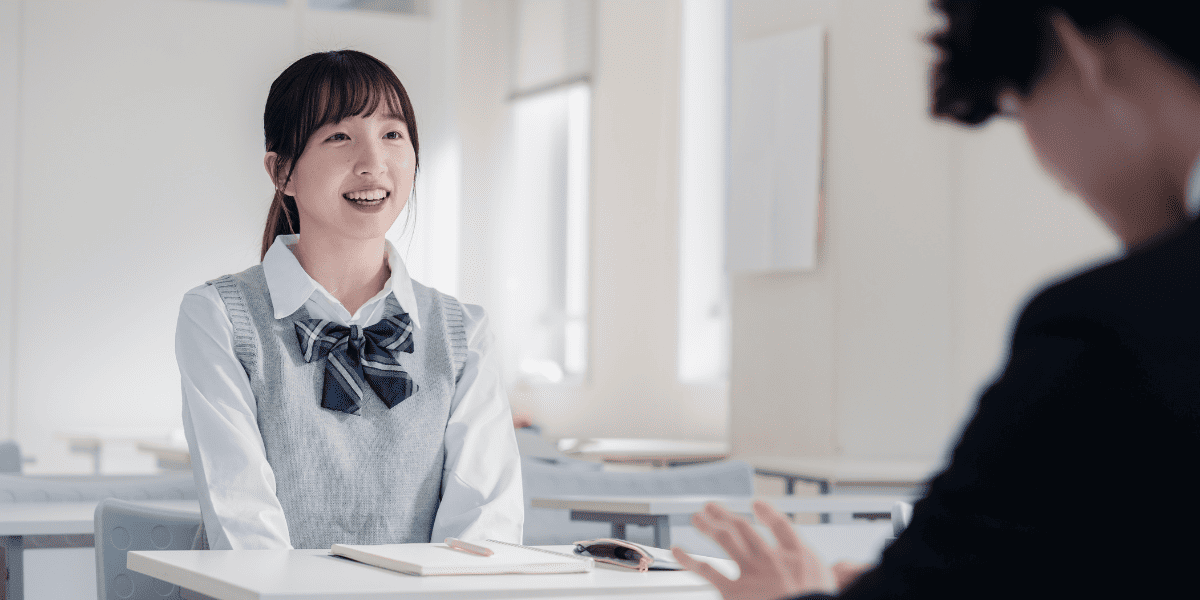
総合型選抜は、通信制高校に通う方や不登校を経験した方にとって、不利になる受験方法と思われがちですが、むしろ通信制高校に通う方や不登校を経験した方にとっては、活用しやすい入試方式といえます。
その理由を詳しく見ていきましょう。
通信制高校の学びや経験がアピール材料になる
通信制高校での学びや多様な経験は、大学入試、特に総合型選抜において、自分だけの強力なアピール材料となり得ます。
通信制高校では、柔軟なカリキュラムの中で自ら学習計画を立て、主体的に学びを進める機会が多くあります。
誘惑と戦いながら計画を実行し、目標を達成した経験は、大学側が重視する「自己管理能力」「主体性」「自律性」といった能力の証明となります。
日々の具体的な工夫や努力のエピソードを交えて語ることで、その能力の高さを効果的に伝えられるでしょう。
多くの大学は、画一的な経歴だけでなく、多様な背景や経験を持つ学生を求めています。通信制高校で過ごした日々は、他の多くの受験生とは異なる、独自の価値ある経験だと考えると良いでしょう。
通信制高校ならではの注意点と対策

通信制高校から総合型選抜に挑戦する際には、強みとなる部分がある反面、いくつか留意しておきたい点と、それに応じた対策がありますので、詳しく解説していきます。
調査書については早めに教員に確認する
まず、調査書の扱いについてです。
通信制高校の成績評価や出欠記録の形式は、全日制と異なる場合があるため、できるだけ早めに担任の先生に相談し、ご自身の調査書の内容を正確に確認しておくことが大切です。
その上で、もし学習状況について補足が必要だと感じたら、自己PR書類などを活用して具体的に説明すると良いでしょう。
選抜に向けたサポート状況を確認する
次に、選抜に向けた対策サポートの状況も確認しておきましょう。
学校によっては、面接練習や小論文指導などのサポートが十分に受けられないと感じるケースもあるかもしれません。
そのような場合には、外部の予備校や進路相談サービス、あるいはオンラインで提供されている対策講座などを積極的に利用することを検討してみるのも有効な手段です。
出欠記録については正直に伝えたうえで意欲をアピールする
そして、出欠記録に関しても配慮が必要になることがあります。
例えば、不登校の経験などから欠席日数が多い場合には、その理由を正直に伝えるとともに、現在は学習意欲が高く、大学での学びに支障がないことを具体的に説明することが重要になります。
大学側は、過去の状況それ自体よりも、そこから何を学び、現在どのような前向きな姿勢で将来への意欲を示しているのか、という点を評価してくれるはずです。
まとめ|総合型選抜とは?視野を広げ、進学の可能性を増やすチャンス

総合型選抜とは、学力だけでは測れない、自分の個性や経験、学習意欲、将来への可能性を大学に伝えることができる入試方式です。
大切なのは「受かりやすい大学」を探すこと以上に「自分に合った大学」を見つけ、その大学が求める人物像と自身の特性を深く理解し、結びつけることです。
そのためには、早期からの計画的な対策が欠かせません。
自己分析を深め、大学研究を徹底し、書類作成や面接練習に真剣に取り組むプロセスは、単なる受験対策にとどまらず、自分自身の将来を考える上で非常に有意義な時間となるはずです。
総合型選抜という選択肢を理解し、自信を持って挑戦することで、自分らしい進路選択の可能性を広げてください。
おすすめコラム